疏水線
sosuisen - the path where water flows.
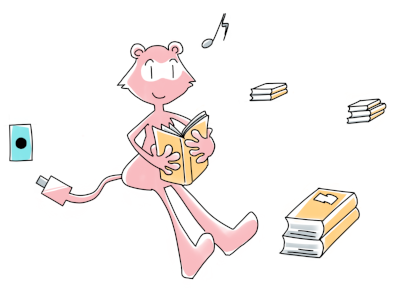
My projects
- GitDocumentDB
Offline-first database that syncs with Git
- Petasti
The sticky outliner
- Logseq (ja)
Logseq 日本語ドキュメントプロジェクト(非公式)
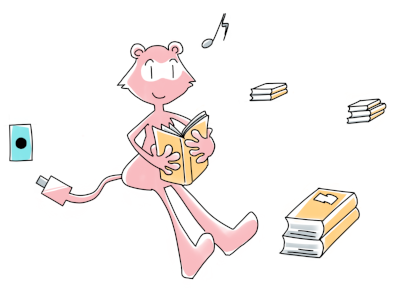
Offline-first database that syncs with Git
The sticky outliner
Logseq 日本語ドキュメントプロジェクト(非公式)